私たちの暮らしに深く関わる「薬」や「食」のルーツをたどると、古代中国に辿り着きます。その原点とも言えるのが、『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』
ここでは、この古典を「いつ・どこで・誰が・何を」書いたのか、4つの視点(4W)で紐解いていきます。
When:いつ成立したのか?
薬の知識が文字になるまで
- 編纂されたのは、今から約1800年以上前、後漢時代(西暦200年前後)
- 実際の知識はさらに古く、戦国時代〜前漢にかけて民間で蓄積された経験がベース
- 中国最古の薬物学書とされ、後の『本草綱目』など多くの医薬書に影響
暦とのつながり
天体の運行にあわせて、365種類の薬物が紹介されており、自然との調和を重んじる思想が見られます。
Where:どこで生まれたのか?
中国全土を網羅したフィールドワークの結晶
- 主に黄河・長江流域を中心とした中国各地が対象
- 高山、湿地、草原、鉱山など、多様な地形と気候から薬材が収集された
薬材の内訳(全365種)
- 植物由来:252種(約7割)
- 動物由来:67種
- 鉱物由来:46種
Who:誰が書いたのか?
神話と現実のはざま
名称の由来である「神農氏」は伝説上の帝王。
百草を舐めて毒を試し、薬効を記録したとされる。農業と医療の始祖。
実際の編纂は?
多くの人々の知恵の集積と考えられます。
- 薬師(薬物の専門家)
- 学者(理論の体系化)
- 巫医(呪術・民間療法の実践者)
- 民間医(地域の経験知をもつ治療者)
口伝と実践によって継承され、やがて宮廷の医官がまとめ上げたとされます。
What:何が書かれているのか?
三段階の分類による薬のグレード
上品(じょうほん)─ 120種
- 無毒で長期服用が可能
- 養命・若返り・病気予防など、日常的な体調維持を目的とした薬
- 代表例:人参、霊芝、甘草、麦門冬
- 現代的には、アダプトゲンやサプリメントに通じる
中品(ちゅうほん)─ 120種
- 効能が高い一方で、毒性を持つものもある
- 病期や体質に応じた選択が求められる
- 代表例:当帰、茯苓、黄耆、麻黄
- 漢方処方や個別化医療の考え方に近い
下品(げほん)─ 125種
- 有毒性が高く、短期間・適切な使い方が前提
- 重病治療や毒の排出などに使われる
- 代表例:附子、大黄、巴豆、烏頭
- 劇薬や抗がん剤の元祖とも言える存在
君臣佐使──薬のチームワーク理論
『神農本草経』には、薬の配合理論として「君・臣・佐・使」の考え方が導入されています。
- 君薬:主役となる主要な薬
- 臣薬:君薬を補佐する薬
- 佐薬:毒性の緩和・補助的な効果
- 使薬:全体の流れを整える媒介的な役割
この理論によって、薬の相互作用や副作用を抑えつつ、最大限の効果を引き出す工夫がなされていました。
味と気──薬の性格を見極める知恵
- 五味:酸、塩、甘、苦、辛
- 四気:寒、涼、温、熱
調剤と服用法
- 調剤法:丸薬、粉薬、煎じ薬、アルコール抽出、外用薬など
- 服用タイミング:
- 胸より上の病:食後
- 腹より下の病:空腹時
- 骨や髄の病:夜間に服用
- 血脈・四肢の病:朝の空腹時
病名とその現代的対応
- 中風:脳卒中
- 霍乱:急性胃腸炎
- 消渇:糖尿病
- 癰腫・瘰癧:腫瘍・リンパ節炎
- 崩中・漏下:不正出血
- 温疫:感染症
- 虫蛇毒傷:毒虫・毒蛇による中毒
現代に活きる『神農本草経』の意義
応用の視点
- 個別化医療の源流
- 統合医療(東洋×西洋)の橋渡し
- 予防医学としての「未病」思想
- 薬の相互作用や配合の知恵
活用が期待される分野
- サプリメントや機能性食品の開発
- 天然物を活かした創薬研究
- 食養生や薬膳理論の基礎
- メンタルケアやストレス医学への応用
Conclusion
2000年前の人々が自然の中で試行錯誤しながら築いた薬草の知識。それが『神農本草経』には凝縮されています。
今を生きる私たちがこの古典を読み直すことで、「人間とは何か」「自然とどう共に生きるか」のヒントが得られるかもしれません。
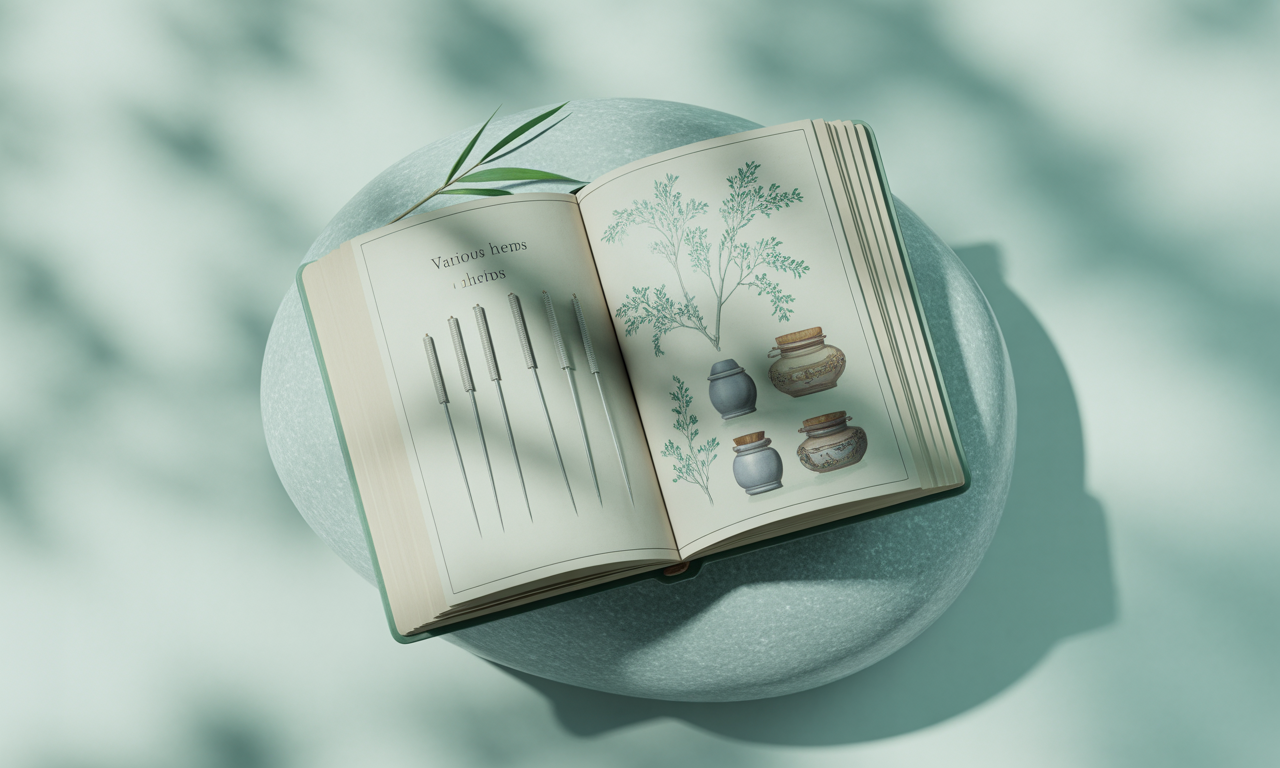
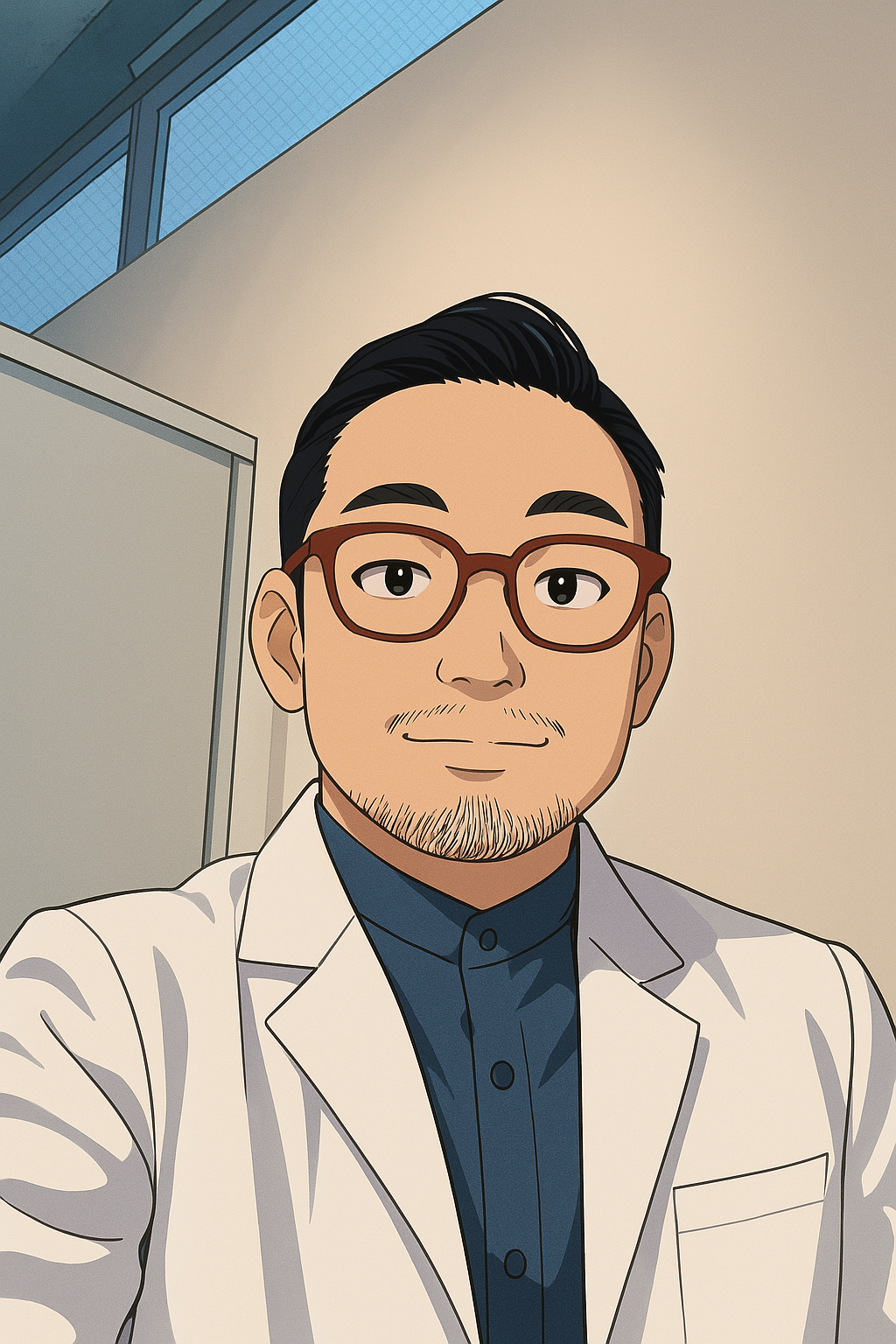
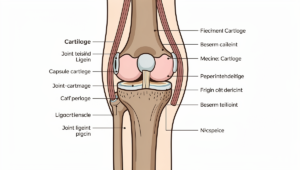


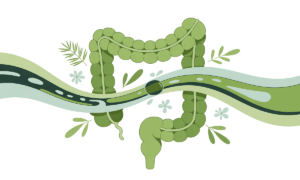
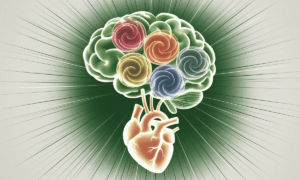


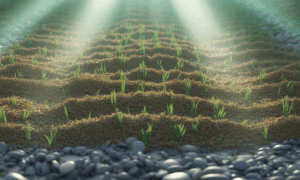
Comments